土工事の雨水対策
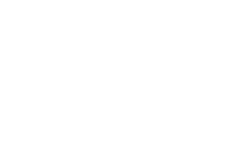
Vol.1
1
2024/11/29
仮設排水
雨水対策の必要性
土工事では、雨が降った際に盛土の軟弱化や濁水の流出などを防ぐための工夫が必要になります。特に「沢」になった地形の部分には水が集まるため、入念な対策が求められます。
Vol.1
2
2024/11/29
仮設排水
竪排水の役割
沢部の水は「竪排水(たてはいすい)」から地下の横方向に設置された雨水管へと流れ、一箇所に集められます。
Vol.1
3
2024/11/29
仮設排水
仮設沈砂池
竪排水によって集められた雨水が集められるのは、「仮設沈砂池(かせつちんしゃち)」です。工事中の排水には砂や土が混じり、濁っていることから、これらを沈めて上澄みの部分を外部に流していくのです。
Vol.1
4
2024/11/29
仮設排水
竪排水の仕組み
砕石が巻かれた竪排水は、細かい穴が空いています。ここから周辺の雨水を管の中に導く仕組みになっています。最終的にはコンクリート等で上部が閉じられるため地表には現れませんが、土工事には欠かせない重要な仮設構造物となっています。
Vol.1
5
2024/11/29
仮設排水
雨水管を埋め戻すときの注意
地中を通っている雨水管は「仮設」とはいえ重要な構造物です。工事中に荷重がかかってつぶれてしまわないよう、埋め戻す際には周囲の土を入念に締固めて、雨水管に影響が及ばないようにしておくことが求められます。
Vol.2
1
2025/01/24
施工中の排水の重要性
工事を再開しやすくする工夫
施工中の排水処理は、用地外への土砂、濁水流出防止の観点で非常に重要です。また、土工事は地面がぬかるんだ状態では、実施できません。そのため、降雨後はできるだけ早く雨水の排水がなされるよう、重機などを使って「水を切る」(溜まった水を流す)ことが行われます。
Vol.2
2
2025/01/24
施工中の排水の重要性
排水勾配について
降雨後の適切な排水を促すため、施工面に設けられるのが「排水勾配」です。これは、両端に向かってゆるやかに傾きをつけることで、施工面に雨水が溜まらないようにするためのものです。これにより雨水の法面への流下を避け、かつ盛土内への浸透水ができるだけ少なくなるようにします。どこからどこへ水が流れるのかに留意して施工することが、土工事の工期と品質に大きく影響します。
Vol.3
1
2025/04/08
日本国土開発の盛土へのこだわり
安全な盛土を施工
地盤を所定の高さまで高めるために土を盛ることを「盛土(もりど)」と呼びます。道路や造成工事など、さまざまな土工事で行われますが、これを安定したものとするためには「水」に対するさまざまな対策が必要となります。日本国土開発では、これまでの知見を活かしながらさまざまな排水対策を施し、安全な盛土を施工しています。
Vol.3
2
2025/04/08
日本国土開発の盛土へのこだわり
盛土の中の水を排出
全国各地で土砂崩れなどの問題が発生しています。その多くは盛土の中に雨水や地下水などが滞留したことに起因するため、いかに盛土の外へ排出するかが重要になります。そこで、水平ドレーンと呼ばれる排水材や砕石、排水桝、パイプなどさまざまな手段を用いて盛土の中の水を排出していくことになります。
Vol.3
3
2025/04/08
日本国土開発の盛土へのこだわり
盛土が安定するまでやる
排水の方法は盛土の計画段階でも検討されますが、意図した通りの場所から出てくるとは限りません。施工を進める中で水が出てくる場合は、その都度水の通り道である「水みち」を見つけ出して排水を促進していくほか、将来を見越した対策も実施します。「盛土が安定するまでやる」。徹底したこだわりが安定した盛土をつくりあげます。
Vol.3
4
2025/04/08
日本国土開発の盛土へのこだわり
自然との戦い
盛土の排水対策は「自然との戦い」であると言えます。必ずしも予測したとおりにはならず、出てくる水を止めるといったその場しのぎの対策では解決にならないばかりか、新たな問題を引き起こします。一方で、水の特性をきちんと理解し、適切に導くことができれば、長く活用できる、安定した盛土とすることが可能です。
Vol.4



